【日本代表コラム】日本代表のバックスをロールに注目して考察する – グラデーション化したロールを分類して考える
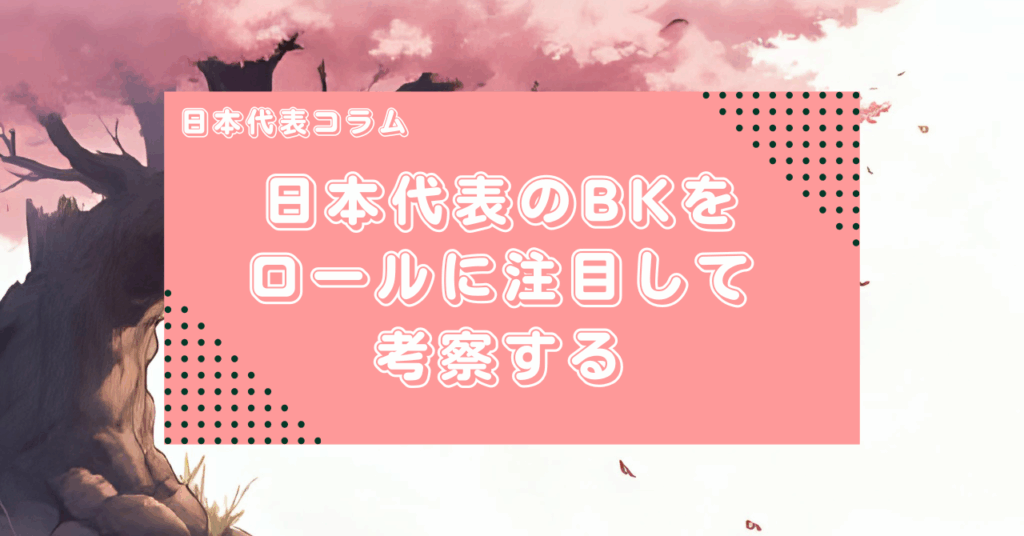
みなさん暑い中いかがお過ごしでしょうか
日本代表のウェールズとの2連戦が終わりました(マオリ・オールブラックスとの試合を含めれば3試合)。
少しずつ今シーズンの日本代表の戦い方といったところが見えてきたところではないでしょうか。
そんな中、Xにて選手の果たしている役割を知りたい、というコメントをいただきました。
実際、近年のラグビーでは、特にBKの選手の役割の多様化が進んでいます。兄弟アカウントでもあるUNIVERSISでも過去に触れてきました。
そこで今回は、日本代表の試合メンバー、特にウェールズとの2連戦に出場したBKの選手に注目して役割ごとに分類できないか試してみることにしました。分類しながらパフォーマンスを考察していきます。
※SHの選手は役割が特にユニークなので、割愛しています。
※呼び方は独自のものです。業界共通ではないのでご注意ください
目次
- フラットプレイメーカー
- SO:李承信
- FB:サム・グリーン
- ディーププレイメーカー
- FB:松永拓朗
- FB:中楠一期
- ナインスマン
- CTB12:中野将伍
- フラットラインメーカー
- CTB13:ディラン・ライリー
すべて表示
フラットプレイメーカー
フラットプレイメーカーは、どちらかというと浅い位置でのゲームコントロールを役割とします。相手に接近してパスを放る傾向にあり、自分からのワンパスでゲームをコントロールしようとします。
SO:李承信
李選手は、リーグワンでは12番や15番を務めていたこともあり、展開力に優れたというよりも、自分のコントロールできる範囲内のプレイングで打開を図るような役割を果たしています。自分でのキャリー比率も一定量見られており、狭い範囲でのコントロールを得意とするタイプに見えます。
ウェールズ戦の第1戦ではジェネラルフェイズでのボールタッチ回数が少なく、ボールをコントロールする機会自体が少なく、2戦では回数が増えたもののうまくコントロールをすることができていなかった印象です。
全体的に少ないパス回数でのキャリーが増えていた様相も見られていました。
個人的な印象としては、李選手のSOとしてのワークレートは、まだまだ発展途上ではないかと感じています。アタック時の展開力には伸び代が感じられ、まだ自分に近い位置でのコントロールに限られているようにも見えました。
FB:サム・グリーン
グリーン選手はリーグワンでは10番を背負っていた選手ですが、交代した際の背番号で言うと15番として試合には投入されていました。
しかし、個人的にはグリーン選手の良さはフラットラインメーカーとしての強さがあると感じています。
グリーン選手はスピードのあるタイプのプレイメーカーで、アタックライン自体にスピードを与えることができます。
キックリターン時のカウンターアタックでも特徴を遺憾なく発揮することができ、素早く相手ラインに向けて体を差し込むことができています。
しかし、ウェールズとの第2戦で出場した際には、少し役割が李選手とかぶってしまっていたようにも感じました。
李選手とグリーン選手では少しタイプが違うため、共存も可能かとは思いますが、フラットプレイメーカータイプであるグリーン選手が深い位置に立っていることも多く、グリーン選手らしさを発揮する機会は多くなかったようにも見えます。
ディーププレイメーカー
ディーププレイメーカーは、アタックラインの深い位置でゲームコントロールを司る選手です。最初のレシーバーとしてゲームを動かすと言うよりは、ラックから見て二人目の選手、二つ目の階層でボールを受けるような立ち位置をとっていることが多く見られます。
FB:松永拓朗
松永選手は、残念ながら第1戦の途中で負傷後退となってしまいましたが、リーグワンの戦いの中で15番として優れたプレイングを見せてきた選手です。松永選手はバックラインの比較的深い位置に位置したり、時に浅い位置どりをしてフラットプレイメーカーのような役割を果たすこともあります。
ただ、個人的には松永選手はディーププレイメーカーに分類できるプレースタイルをしています。
中央を自力で突き崩す能力よりも、外に生まれたギャップをつくことに長けており、深く遠い位置からスピードを持ってギャップに仕掛けるシーンが多く見られていました。
パス能力や視野にも長けているため、大きく前に出た後の選択を外すシーンも少なく、安定したプレイングを見せています。
代表戦では負傷の影響で長いプレー時間がありませんでしたが、第1戦で生まれたトライに関わっていたりと、ポジショニングの能力は見ることができたかと思います。
FB:中楠一期
中楠選手は、ディーププレイメーカーの中でも表と裏の両方に選択肢を作ることができる選手です。今回のウェールズとの2連戦、リーグワンで務めていた10番とは違うポジションでの出場となりましたが、深い位置でのゲームコントロールを主軸に、浅い位置での選択肢としてのプレイングも光っていました。
特徴的だったのが第2戦の前半に見せたビッグゲインで、通常時であれば2枚目の裏に入ることが多かった中楠選手が、このシーンでは表のラインでディラン・ライリー選手からボールを受けていました。
スピードとアングルも的確で、1回のパスの動きだけで大きなゲインを手に入れていました。
ただ、今回の2試合では15番、ディーププレイメーカーとしての役割をこなすことが多かった中楠選手ですが、個人的には浅い位置でのプレイング、フラットプレイメーカーとしてのロールも見てみたい気持ちです。
突破力では他の選手に軍配が上がるかもしれませんが、ファーストレシーバーとしての能力は高いため、可能性が見られるかもしれません
ナインスマン
ナインスマンとは、主に12番の選手がこなすことの多いロールで、FWとともにポッドを作ることが多いのが特徴です。パスの頻度は一般的な12番よりも控えめで、接点に強みのある選手が該当する場合が多く見られます。
CTB12:中野将伍
中野選手は、サンゴリアスでは器用で接点に強いタイプのキャラクターですが、代表では接点の部分のワークレートが特に重要視されているように感じます。
9シェイプ・10シェイプ問わずポッドに参加してFWと同じようなロールをこなすことが多く、中盤での展開を担っているシーンはあまり見られなかったのではないかと思います。
中野選手の持ち味は恵まれた体格による接点の強さです。安定したコンタクトを見せており、シーンによってはオフロードを繋ぐといった器用さも見せることがあります。
実際に試合を見る限りでも、接点の部分では十二分に戦えていたことが印象に残っています。
しかし、実際のところ2試合目ではミスが目立つ結果になっていました。
私は、これの要因として「役割の過多」があると考えています。
本来であれば器用さから展開にも強みがある中野選手ですが、今回のシリーズでは接点に偏った運用をされていたように感じました。
基本的にボールを持てばキャリーに繋げ、展開時もFWとしての動きが目立っています。
その結果としてプレーの精度が下がり、後半のワークレートの低下につながったのではないかと思います
フラットラインメーカー
フラットラインメーカーは、アタックラインを構成する選手のうち比較的浅い位置でプレーする選手です。展開と接近戦のバランスもとりながら、キャリーでも強みを発揮する選手が当てはまります。
CTB13:ディラン・ライリー
ライリー選手は、ブレイクした後のスピードも含め、全体的にバランスの整ったランナーの一人です。ハンドリングの器用さもあり、キャリーから繋ぐことにも長けています。
ライリー選手のウェールズ戦での運用としては、どちらかというとキャリー寄りの働き方であったように感じます。展開を司るといったパターンよりも、早い段階でボールを受け、そのままキャリーに持ち込むパターンが多く見られました。
運用の是非については難しいところですが、ライリー選手の鋭い突破力とハンドリングを生かそうとする流れの中では比較的妥当な運用であったと感じます。
一方で、ライリー選手が少しラックから近い位置での運用となっていたため、ライリー選手のスピードを生かしきれていないようなシーンもあったように思います。もう少しプレイングエリアを外側にするなどの工夫ができるかもしれません。
スプリンター(仮名称)
スプリンターはBKの全タイプの選手の中で特に走力に優れたタイプであると定義しています。スプリンターはエッジで運用され、外で生まれた数的優位を突いて相手を振り切るようにプレーするのが特徴です。
WTB11:マロ・ツイタマ
ツイタマ選手はブルーレブズでも外側のエリアを主戦場としています。外側で生まれた空間を生かし、スピードを使ってトライまで取り切ることを得意としています。
ウェールズとの2連戦では1戦目に出場し、環境などに苦戦しながらの途中交代となりました。アタックラインの深い場所に位置し、展開する役割も任されていたように感じます。
ただ、キックレシーブなどで特に苦戦していたようにも見えました。
キックレシーブに関しては環境要因も影響しているかもしれませんが、改善すべき因子ではないかと感じられます。
また、バックラインの中間地点としてライン参加した時の不安定さも気になる部分ではないかと思います。
求められるロールとしてはマルチタスクの様相もあるので、この辺りの調整が待たれるかもしれません。
WTB14:石田吉平
石田選手はスプリンターであり、ステッパーでもあります。役割としては大外で距離感をキープしながら数的優位性を活用するようにランニングを見せることです。石田選手はツイタマ選手とは異なり明確にインサイドに仕掛けるシーンは少なめで、セットプレーからのフェイズで仕掛け役になるくらいではないかと思っています。
ウェールズ戦の第1戦ではセットプレーからの一連のフローに絡み、スピードとアングルを生かしながら効果的なアタックに繋げていました。それ以外のシーンでも、スピードと足腰の強さを生かしてエッジでの前進に貢献していました。
ハイボールでも、ある程度の強さは見せていたように思います。高さ自体はより大柄な選手に劣る部分はあるかと思いますが、再獲得のチャンスを掴むことはできていました。
それ以外の部分でも安定感のあるプレイングを見せており、主たるロールの部分はこなすことができていたように感じます。
ペネトレーター(仮名称)
BKの選手のうち、突破力に優れた選手として定義しています。パワー系のランナーが該当することが多く、走力と接点の強さが特徴になっています。
WTB11:ハラトア・ヴァイレア
ヴァイレア選手はエッジに配置されることが多く、エッジで突破力を生かしながらトライを取ることを得意としている選手です。
数的な優位性が作れていないシーンでも相手を巻き込んで前に出ることがでできるため、外側のエリアでパワープレイに繋げることができます。
ウェールズとの2連戦では、1戦目の途中交代、2戦目の先発として出場しています。試合ではエッジに近い位置での突破役として活躍し、複数人を巻き込みながら前に出るシーンを見せていました。
その他のパワープレイも安定しており、エッジでの切り札の一つとしていいプレーを見せていたように感じます。
一方で、少し課題となったのはハイボールの確保の部分です。回数自体はあまり見られなかったのですが、ハイボールを競り合う段階での「高さ」の部分での不安定性がありました。
ペネトレーター系の選手は苦手とすることも多いのですが、インターナショナルではキックの重要性が高まる都合上、この部分には安定感が必要かもしれません。
まとめ
これらのように、チームから任されているであろうロールと、得意とするロールが重なっていないような選手も見受けられているように思います。
どちらに合わせるかはHCの匙加減になってくるかと思いますが、現状としては、一定の調整は必要かもしれません。
ロールはアタックの狙いに沿った組み合わせで効果を発揮するので、うまい組み合わせを模索していきたいものですね。
それではまた。
1994年生まれ、東京出身。九段中等教育学校→筑波大学。大学・大学院での学生トレーナー経験を経てNECグリーンロケッツでアナリストとしてのキャリアをスタートする。NECグリーンロケッツ東葛で2年間活動し、退団後はフリーアナリストとして個人・団体からの依頼で分析業務に携わる。また、Webマガジン「Just Rugby」にて分析記事を連載中。