【マッチレビュー】2025大学ラグビー関東対抗戦:明治大学対筑波大学
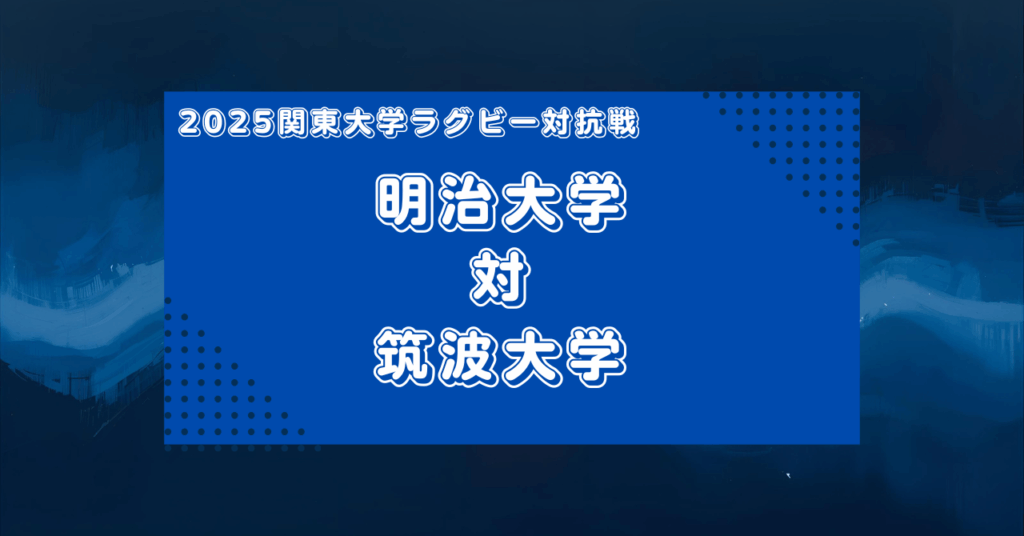
一進一退の接戦の最後に、劇的な逆転劇
みなさんこんにちは
遂に大学ラグビーのシーズンが始まりました
今回は関東大学対抗戦より、9/14に行われた明治大学対筑波大学の試合について、見ていきたいと思います
明治大学のラグビー
<今節の明治大学>
明治大学は、リーグ屈指のFW陣と、決定力のあるBK陣でバランその取れた攻守を見せるチームです。接点に定評があり、前に出る力は日本全国を見てもトップレベルでしょう。
チームのタクトを振るうのはSOの伊藤龍之介選手で、ラン・パス・キックのバランスがいい万能型の選手でありながら、中でもランニングスキルは高水準にあり、攻撃面で突出した能力を持つ選手です。
そんな明治大学ですが、今回の試合では「らしくない」ポイントがいくつか見られました。一般的な戦略の範囲内では正道とも言える戦略性を見せていましたが、それは得てして明治らしくないとも言える状況でした。
<苦戦したラインアウト>
最も顕著に現れた例としては、ラインアウトの成功率の部分ではないでしょうか。19回の試行回数に対して11回の成功と、半数近いラインアウトをミスで失っていることになります。筑波大学側のラインアウトスティールを受けたりと、かなりプレッシャーを受けていた側面が見受けられ、不安定さにつながっています。
明治は、そういった状況に対して、ラインアウトの一番前で取る、という戦略をとっていました。後半に生まれた西野帆平選手のトライはその最たる例で、ジャンプを解さずにダイレクトに確保することでミスを低減することができます。
しかし、ここに明治大学としての難しさを感じました。戦略的な正道で言えばこの選択は間違いのないものであるように思います。しかし、明治としてこの選択が正しかったかというと、メンタリティの部分も合わせて不安定になる要因にもなったかもしれません。
<アタックの傾向>
アタック全体としては、非常にいい傾向を見せていました。接点で上回り、リズムを出して相手の反則を誘発する。明治らしさもありながら「こうすれば相手が崩れる」というパターンに試合を持ち込んでいました。
アタックは接点の他にも階層構造を用いて展開を図るシーンもあり、表と裏の構造を使っています。特に相手陣に向かって前進し、モメンタムを獲得できている時に構造的なアタックを使い、深さを生み出しながらさらにモメンタムを出すことに成功しています。
また、主体的にキックを使ってエリアコントロールやプレッシャーをかけていました。自陣寄りではロングキック、中盤ではハイパントを交えたりと、戦略的なキックゲームに持ち込んでいました。
ただ、ここも試合展開として難しいところで、個人的な視点としては、中盤での明治の怖さは「展開してくる」ところにあると思っています。伊藤龍選手の展開力と走力、その他の選手の機動力と接点の強さが揃っていたりと、展開するには十二分の力を発揮します。
しかし、明治はそこまで展開にこだわらず、戦略的な攻防を続けていました。結果として、戦略性の範囲内でのスコアに留まっていたという見方をしています。
敵陣深くでFW戦に持ち込むことができれば明治の強さを発揮できるのですが、明治はラインアウトに不安定感があり、ゴール前では消極的な選択が中心となっていました。結果としてエッジでのトライになってゴールを狙いづらかったりと、さまざまな要素にラインアウトの不安定感が影響していました。
<ディフェンスの傾向>
ディフェンスも悪くはない部分が多かったとは思います。接点でも強く、規律正しいディフェンスを見せており、筑波大学のアタックの多くを下げることに成功していました。
しかし、それも接点の土俵に立った場合の話で、接点以外の部分に関しては互角か押し込まれるような展開になっていたように思います。
特にエッジの部分のディフェンスでは、崩された多くの場合でFWとBKのミスマッチを作られています。
前半に奪われた2トライは、どちらもカメラから見て手前側のサイドを活用された形でした。1つ目のトライは展開の中でFWが偏って配置されてミスマッチを突かれ、2つ目のトライはチェイスラインで唯一のBKであった白井瑛人選手選手がタックルを外されたことによって、BK2人と走力のあるFLに対してFWが2人という状況に陥っていました。
また、最後の筑波大学の逆転につながったトライのシーンでは、2フェイズ前に明治大学の選手が規律的に順目方向に4人回ってしまい、結果として逆目方向に通されたアタックをBKである海老澤琥珀選手が止めざるを得ない状況になっていました。海老澤選手がタックルをしたことでさらに外側のエリアのディフェンスが薄くなり、トライに繋げられています。
筑波大学のラグビー
<今節の筑波大学>
筑波大学は、接点とブレイクダウンに強みを持つ、上位校食いをすることもあるチームです。泥臭くプレーをすることを得意としています。
筑波大学は、9番の高橋佑太朗選手と10番の楢本幹志朗選手が、うまく試合展開をコントロールしていたように見えました。
高橋選手は攻撃的で、楢本選手は安定型の思考をしており、キックを主体に試合を動かしていました。
特に蹴り合いになった時の楢本選手のキックの精度は高く、単純なキック距離で負けてしまっている時も、前に仕掛けながら左足で放つキックによって、最低限稼いでおきたいラインは越えることができていたように思います。
<効果的に働いたアタック>
今回の試合では、特にエッジに展開するようなアタックが効果的に働いていたように感じました。必ずしも大きな展開ではなくとも、エッジでのショートパスで打開しています。
ここ数年の明治のディフェンスを見ると、中盤での厚さがある反面、エッジでは比較的ゲインを許すなど、アンバランスな堅さのあるチームでした。
夏合宿の帝京大学戦など、展開力のあるチームに対しては少し苦戦傾向にある印象です。
筑波大学は、大まかにいうとエッジをうまく活用していました。エッジからエッジのような大きく展開するような形ではなく、ショートサイドのエッジを攻略しています。
前述したように明治のディフェンスはラックから近いエリアが堅く、つまりラックの位置によってはFWが固まっているような状況が生まれています。そのシーンに対して、楢本選手は細かなサイドチェンジや状況判断で狭いサイドに優位性がある時はそこを狙い、走力のある中森真翔選手をエッジに配置することによって質的にも上回る状況を作り出していました。
<アタックの傾向>
筑波のアタックは比較的シンプルで、接点にこだわりの見える形です。9シェイプを多く用い、12番の今村颯汰選手や13番の東島和哉選手といった縦に出られる選手も交えながら、コリジョンで中盤のアタックを安定させています。
また、今回の試合では前述したようにキックでエリアをコントロールしている傾向も見られました。中盤でのアタックでは苦戦していた様子もあり、早めに蹴り込むことで中盤でミスが起きたりする前にボールを前に運ぶことができていました。
キックがタッチに出ればプレッシャーをかけ、タッチに出なくても相手の蹴り返しを待つことができるので安定感が見られています。
基本的には1−3−3−1のような配置を取り、エッジに走力のある中森選手のような選手を配置しています。中盤はタイトファイブの選手とNO8の大町尚生選手を配置して安定したコンタクトを見せ、楢本選手がボールを動かしながら接点を作り出していました。
ただ、全体的にブレイクダウンでは苦戦傾向にあったように思います。接点の強い明治に押され、人数をかけなければいけなかったり、スティールを狙われて反則を犯したりと、難しい展開でした。
<ディフェンスの傾向>
ディフェンスもどちらかといえば苦戦していたという見方をすることができます。相手の接点が強く、一部の選手には大きく前に出られていたりもしました。
ただ、組織的なディフェンスの部分では多くのシーンで相手を止めることができていたように思います。タックルも低く入ることができており、アシストタックルの精度の高さも見せていました。
一方で、ペナルティのうちの多くはディフェンス時に発生したものであり、相手がモメンタムを出し始めた時にペナルティを犯してしまったりと相手にポゼッションを献上するようなシーンも見られていました。
まとめ
結果としては、筑波大学の逆転勝利という形にはなったが、トライ数は共に4トライと、互角の結果を示している。また、試合全体のモメンタムを見ても、再戦して必ずしも同じ結果になるとは限らない。
筑波としても、「トライをとって残り2分」ではなく「トライを取られて残り2分」というポゼッションになったのも影響しているかもしれない。トライをとった場合は残り2分で相手キックオフ、トライを取られた場合はこちら側のキックオフとなるため、時間の使い方が変わってくる。
むしろ、ここからの明治には期待しかないだろう。どの強豪校にも言えることだが、一度負けたチームは必ず強くなる。ここで負けてよかった、と言えるようなシーズンになることを期待したい。
(文:今本貴士)
1994年生まれ、東京出身。九段中等教育学校→筑波大学。大学・大学院での学生トレーナー経験を経てNECグリーンロケッツでアナリストとしてのキャリアをスタートする。NECグリーンロケッツ東葛で2年間活動し、退団後はフリーアナリストとして個人・団体からの依頼で分析業務に携わる。また、Webマガジン「Just Rugby」にて分析記事を連載中。