【マッチレビュー】2025関東大学ラグビー春季大会Aグループ:早稲田対大東文化を質的分析で見てみた
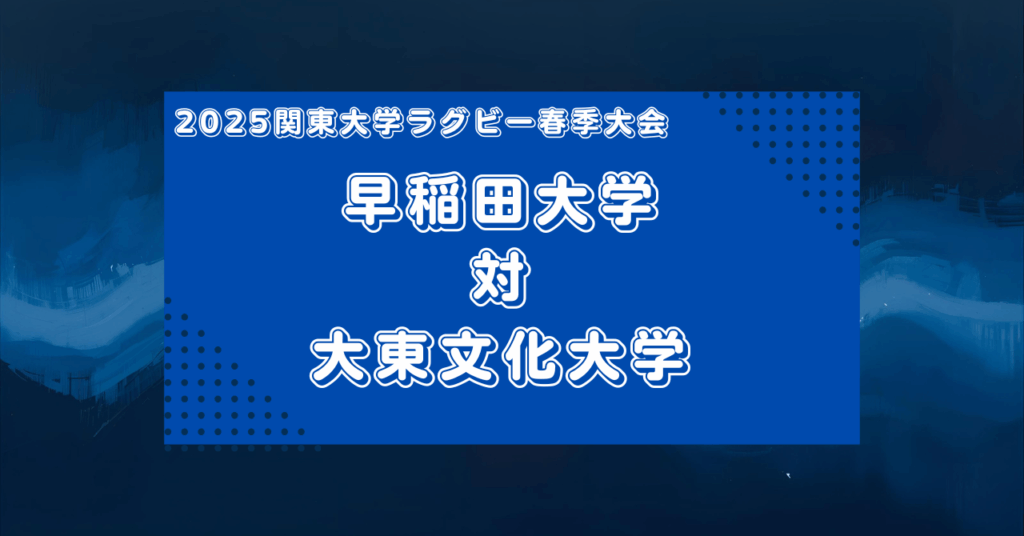
今シーズンも、大学ラグビーが始まりました。
みなさんも、お待ちかねのことだったと思います。
今回は、4/20に行われた関東大学春季大会より、早稲田大学対大東文化大学の試合について、分析をしてみました。
アングルの都合上、質的分析のみとなることをご容赦ください。
それでは、見ていきましょう。
早稲田大学のラグビー
・10番起点のアタック
早稲田のアタックの中心となっていたのは、今シーズンも服部亮太選手だったように感じます。
SHの糸瀬真周選手とのコンビネーションでグラウンドを広く使い、ボールを積極的に動かしていました。
昨シーズンから注目する材料になっていましたが、服部選手は走力にも優れるタイプのプレイメーカーで、今回の試合でもステップを効果的に用いてノミネートされた相手との位置関係をずらしていました。
外に膨らむような動きから鋭角にステップで切れ込むこともできるので、ビッグゲインこそ少なかったものの、ノミネートがずれて相手の他の選手が寄せられることによって、ある意味強引に局地的な数的優位性を作ることもできていました。
また、キックも相変わらずの飛距離です。
中盤で相手のキックを受けた際には距離のあるパントとロングキックの中間のようなキックを蹴り込み、キックを受けた選手に対して激しいプレッシャーをかけていました。
対空時間も長く、本来であれば味方が追いつきづらいような距離のキックであっても、十分に間に合うほどの時間を稼ぐことができていました。
アタックの主体は9シェイプでしたが、それと同程度に用いられていたのが10シェイプです。
10番に入った服部選手に対して3人の選手が配置され、選択肢を作っています。
この10シェイプの構築が他のチームと少し異なる部分で、多くの場合では3人の選手が服部選手に対してオープンの位置に並んでいます。
しかし、一定数のフェイズにおいて、2人と1人にスプリットをして、オープン側に2人、内側に1人というアタックの組み方をしていました。
このようなスプリット形式の配置によって、相手にとって選択肢を押し付けることができます。
普通の10シェイプではオープン側に並んだ3人の集団の、大体が中央の選手にパスを放ることになります。
この場合、3人がまとまっていることでラック形成の際に安定感が出るというメリットがあります。
これに対して、2人と1人にスプリットをすることで、内と外のパス選択肢が生まれます。
3人の集団では1方向でしかなかったアタックフローが、スプリットをすることで2方向に選択肢が生じます。
2人側の配置を、2人をフラットに配置することによってさらに投げ分けの選択肢が生まれ、バリエーションを増やしていました。
服部選手はパススキルも高く、投げ分けによってワンパスでモメンタムを作り出すことができます。
一つのパスで動く盤面ですが、大きな効果を示していると言えます。
・アングルと接点
早稲田のアタックは、今回の試合に関しては接点に比重を置いていたように感じます。
アタックの中で数的優位性を作って外展開をするといったシーンはそう多くはなく、中盤からのビッグゲインでトライまで取り切るといったシーンはそう多くなかったように見えました。
前述した9シェイプと10シェイプもそうですが、アタックの肝となっていたのはボールを受ける際のアングルです。
9シェイプの中で生まれたティップオンパスに対してアングルをつけて走り込んだり、12番と13番のコンビネーションからなるアングルをつけたアタックなど、単なる接点ではなく、瞬間的な位置的優位性を作り出すことにこだわっていたように感じました。
特に優れたアングルを見せていたのは13番の金子礼人選手です。
12番の黒川和音選手とのコンビネーションで、相手にジワリと仕掛けた黒川選手に対して近いエリアに向けてアングルをつけながらキャリーに至っていました。
体も強く、真正面からタックルを受けなければ安定したキャリーにもつながっており、ゴール前のアタックではリズムを作ることにも貢献していました。
また、8番に入った城央祐選手もキャリーで優れたシーンを見せており、アングルをつけた走り込みで、相手の上に乗るキャリーを見せていました。
ゴール前でのアタックでは2本のトライを取ったりと、チームのモメンタムを活かしつつも、体の強さを活かした突貫を見せていました。
早稲田は得点に対して相手を崩し切った回数はそう多くはなかったように感じています。
ただ、相手をドミナントするキャリー、つまり相手のタックルの上に乗ったり相手のタックルを受けながらも前進するキャリーをこなすことによって、相手のミスやペナルティに繋げ、結果として敵陣でのセットピースに繋げていました。
・激しいディフェンス
ディフェンスでも、相手のアタックを効果的に封じ込めていたように見えました。
接点の位置を完全に押し込みながらディフェンスを続け、相手アタックラインとの間に生まれる空間を積極的に埋めるようなディフェンスをしていました。
タックルは低く、激しさの伴うもので、接点が弱いわけではない大東文化のキャリアーに対して、前に出られることなく倒し切っていました。
少し飛び込むようなシーンも見られましたが、シーズンの深まりにつれて修正も容易である部分であると思います。
結果的には4トライを奪われていますが、1トライは個人のスキルの部分、2トライは早稲田側のミスからダイレクトにターンオーバートライを奪われた形でした。
ジェネラルフェイズのディフェンスで崩されたシーンは多くなかったので、自信のつくディフェンスフローではなかったかと思います。
大東文化大学のラグビー
・階層構造とエッジアタック
大東文化は、ある程度階層構造を使った攻略を意識したアタックをしていたように見えます。
10番の伊藤和樹選手のボールのもらい方とチャンスの活かし方を見ると、階層構造をダイレクトにラインブレイクに活かそうとする様子が見受けられるからです。
アタックの構造としては一般的なものに準じたもので、9シェイプと10シェイプに、フェイズに応じて3人の選手を配置する形かと思います。
昨シーズンは4人ポッドを組んでいるように見えるシーンも散見されていましたが、今回の試合では明確な4人ポッドはなかったように感じます。
アタックの基本イメージとしては階層構造を活かしていこうとする様子が見られていますが、多くのフェイズでワンパスで相手とのコンタクトが生まれるシーンが目立っており、ボールを動かし切れなかったようにも感じました。
アタックのフローとしては、エッジを指向したアタックがうまくいっていたように見えました。
階層構造を用いて崩しを生み出したシーンは見ている限りでは一度きりでしたが、中央エリアでの連続アタックからエッジを狙ったアタックでは、数的優位を生かして大きな前進を見せていました。
流れの中でアタックに幅を持たせ、幅を活かしていたように思います。
ただ、アタック自体のテンポは早稲田と比べるとゆったりとした形で、流動的に優位性を作ることもできておらず、ゲイン獲得自体はかなり苦戦していたように見えました。
また、パス回数を重ねることができたアタックではある程度攻略の糸口のようなものは見えていたと思うので、もしかすると接点の作り方の部分に工夫の余地はあるかもしれません。
個人の領域でも、15番のタヴァケ・オト選手のようなスキルフルな選手もいて、活かしどころの工夫で攻撃力の向上も図れると思います。
・苦戦した接点
接点としては、かなり苦戦した方ではないかと思います。
チームのスタイルとしてはある程度接点で前に出て、相手との間に空間を作ることでアタックに工夫を加えるような形ですが、肝心の接点の部分で相手に空間を奪われ、余裕を失っていました。
アタックの中心であるポッドを使ったアタックですが、理想的な形としてはポッドの選手が走り込みながらプレー選択をする、もしくは止まるくらいの勢いでボールを受けてそこからプレー選択をする、といった形が考えられます。
しかし、今回の試合では、素早い出足の早稲田のディフェンスにプレッシャーを受けることによって、その選択肢を選び取るという時間を奪われていました。
シンプルなコンタクトに終始し、優位性のあるコンタクト姿勢を作れたシーンもそう多くはなかったように見えました。
ポッド内でのパスワークといった工夫もあり、接点での圧力をずらそうとする意図は見えました。
ただ、パスをする選手と受ける選手が同じ角度で走っていることで相手としては押さえやすくなり、パスをする選手の相手とのコミットも甘いために読まれやすかったという側面はあるかと思います。
また、ブレイクダウンにもかなりプレッシャーを受けていたように思います。
ジャッカルを受けるだけではなく、サポートに入った選手にコミットされることによってラックの周りの空間を押し込まれ、ボール出しにも苦労していたように見えます。
まとめ
大学ラグビーの春シーズン、最初の分析は早稲田大学と大東文化大学の試合からでした。
早稲田は主力の代替わりや、U23への派遣などでまだまだ固まっていないスコッドだったように思います。
とはいえ、高い攻撃力でゲームを支配していました。
ここに主力が戻ってくるのが楽しみです。
大東文化は昨シーズンのリーグ王者ですが、大学選手権では京都産業大学に敗れるなど難しいシーズンでもあったと思います。
主力の卒業などもあり、ここからの組み立てが大事になってくることでしょう。
今回は以上になります。
それではまた。
(文:今本貴士)
1994年生まれ、東京出身。九段中等教育学校→筑波大学。大学・大学院での学生トレーナー経験を経てNECグリーンロケッツでアナリストとしてのキャリアをスタートする。NECグリーンロケッツ東葛で2年間活動し、退団後はフリーアナリストとして個人・団体からの依頼で分析業務に携わる。また、Webマガジン「Just Rugby」にて分析記事を連載中。